-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
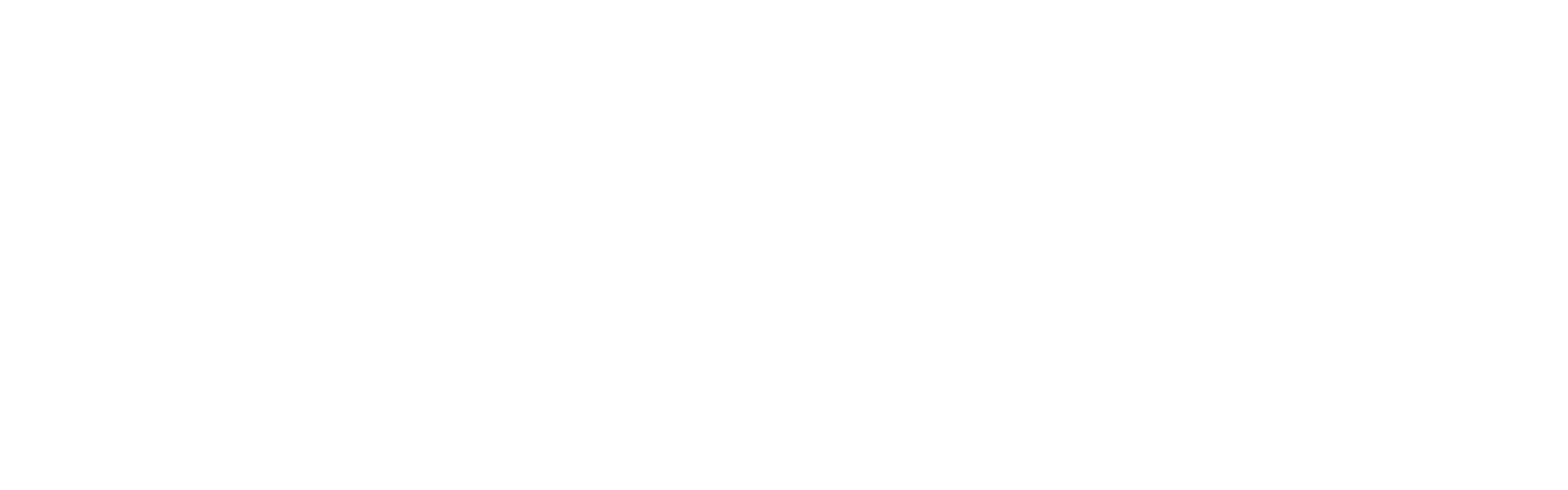
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
木材の“良さ”は目に見えない。
だからこそ、第三者認証=合法・持続可能・トレーサブルを可視化することで
「信頼」をビジネス価値に変える。
本稿では FSC/PEFCの基本構造〜運用・コスト・販路拡大までを整理します。
FM(Forest Management)
森林管理の適正さを認証。
→ 施業・生物多様性・地域合意・労働安全などを審査。
CoC(Chain of Custody)
産地から製品まで、認証材が混ざらず(または按分ルールで)流通していることを証明。
→ 製材・流通・加工・販売の各段階で必要。
FSCとPEFCの違い
| 項目 | FSC | PEFC |
|——|——|——|
| 成立 | NGO主導(国際本部=ボン) | 各国相互承認ネットワーク |
| 強み | グローバルブランド・認知度 | 地域材・中小事業者対応力 |
| 使い分け | 海外・輸出・建材 | 国内・公共・林業系 |
「どちらが上」ではなく、取引先・市場特性に合わせて選定/併用が現実的。
入札・商談のパスポート
公共調達、大手デベロッパ、量販店では「認証 or 合法性証明」が最低条件化。
価格プレミアムより“継続取引”効果
棚確保・返品率減・指名入札増など、“見えない利益”が長期的に効く。
リスク低減効果
違法伐採・人権・労安・環境問題によるレピュテーションリスクを低減。
→ 「損害回避=利益確保」。
“取れる利益”より、“失わない信用”を生むのが森林認証の真価。
識別:認証材は色タグ/スタンプ/QRコードで明示。
→ 非認証材と置場を完全分離。
記録:出荷伝票・受入検収に**認証ID+数量(m³/本数)**を記載。
→ 写真台帳で証跡を保存。
棚卸:月次で認証在庫を照合。差異→原因・対策を即日記録。
教育:ラベル使用・ロゴ表示ルールを1枚シート化(写真付き)。
“ラベル貼りミス”は認証取り消しに直結。現場教育を最優先に。
| 区分 | 内容 | 回収ポイント |
|---|---|---|
| 初期費用 | 審査・マニュアル整備・教育・資材 | 補助金・団体共同取得で圧縮可能 |
| 運用費 | 棚卸・記録・年次審査・ラベル費 | 社内標準化で負荷軽減 |
| 回収方法 | 新規販路開拓・既存顧客維持・見積加点・ESG金融 | 長期的にROI>1を実現 |
“コスト”ではなく、営業投資+金融格付け強化と位置付ける。
公共調達:合法性・持続可能性証明に最も明確な手段。
企業方針:ゼロデフォレ・人権DD要件にCoC文書が流用可。
越境リスク:EU・米・豪など、輸入規制は合法証明を義務化。
→ “最初から認証”のほうが安く早い。
グローバル取引では「認証なし」は取引除外リスク。
ロゴ使用ルール
- サイズ・余白・配置に厳格基準あり。
- 誤表示=信用失墜+契約違反。
B2B資料
認証番号・対象範囲・更新日・証跡フロー図を1枚A4で営業即提示。
B2C発信
「森 → 製品 → 暮らし」のストーリーと地域性で、
“同じ木でも選ばれる理由”を訴求。
「環境配慮」ではなく、「品質と信頼を示す証拠」として伝える。
1️⃣ 認証材の置場を認証/非認証で分割(即日対応)
2️⃣ 出荷伝票に認証ID欄を追加し、写真台帳と連携
3️⃣ 営業用の1ページ説明資料(番号・範囲・更新日)を作成
FSC/PEFCはブランドではなく信用通貨。
「合法性・持続可能性・トレーサビリティ」を
証拠で語れる会社が選ばれる。
森林資源の信頼を“データ化”する仕組みを持つことが、
次世代の競争力になります。