-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
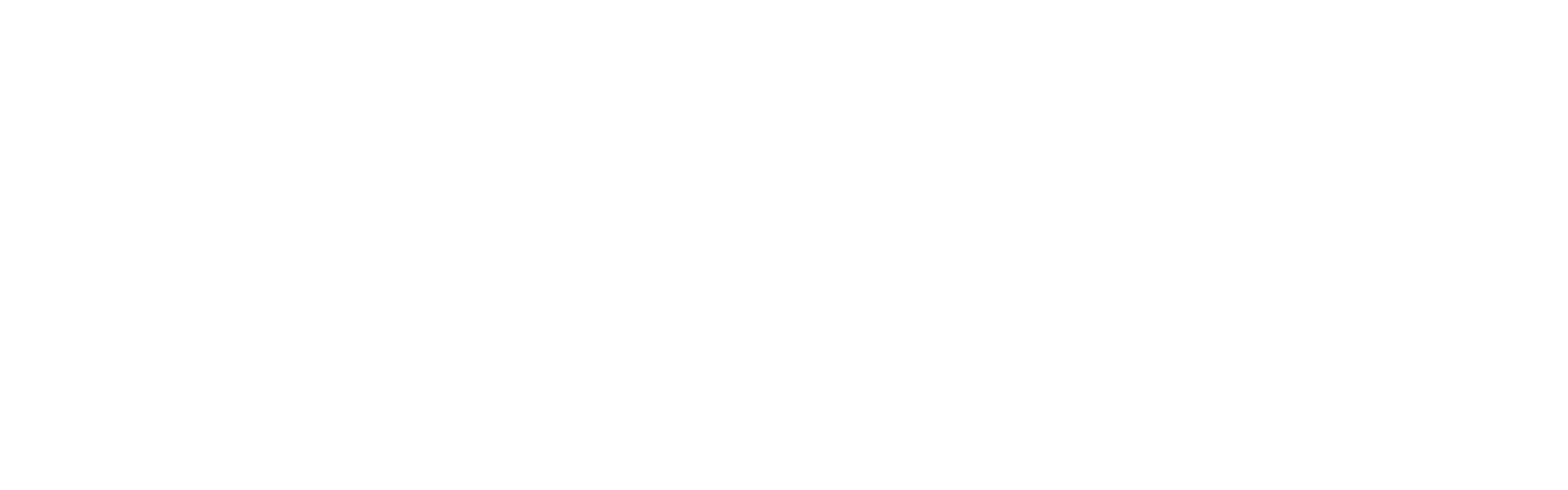
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
木材の“良さ”は目に見えない。
だからこそ、第三者認証=合法・持続可能・トレーサブルを可視化することで
「信頼」をビジネス価値に変える。
本稿では FSC/PEFCの基本構造〜運用・コスト・販路拡大までを整理します。
FM(Forest Management)
森林管理の適正さを認証。
→ 施業・生物多様性・地域合意・労働安全などを審査。
CoC(Chain of Custody)
産地から製品まで、認証材が混ざらず(または按分ルールで)流通していることを証明。
→ 製材・流通・加工・販売の各段階で必要。
FSCとPEFCの違い
| 項目 | FSC | PEFC |
|——|——|——|
| 成立 | NGO主導(国際本部=ボン) | 各国相互承認ネットワーク |
| 強み | グローバルブランド・認知度 | 地域材・中小事業者対応力 |
| 使い分け | 海外・輸出・建材 | 国内・公共・林業系 |
「どちらが上」ではなく、取引先・市場特性に合わせて選定/併用が現実的。
入札・商談のパスポート
公共調達、大手デベロッパ、量販店では「認証 or 合法性証明」が最低条件化。
価格プレミアムより“継続取引”効果
棚確保・返品率減・指名入札増など、“見えない利益”が長期的に効く。
リスク低減効果
違法伐採・人権・労安・環境問題によるレピュテーションリスクを低減。
→ 「損害回避=利益確保」。
“取れる利益”より、“失わない信用”を生むのが森林認証の真価。
識別:認証材は色タグ/スタンプ/QRコードで明示。
→ 非認証材と置場を完全分離。
記録:出荷伝票・受入検収に**認証ID+数量(m³/本数)**を記載。
→ 写真台帳で証跡を保存。
棚卸:月次で認証在庫を照合。差異→原因・対策を即日記録。
教育:ラベル使用・ロゴ表示ルールを1枚シート化(写真付き)。
“ラベル貼りミス”は認証取り消しに直結。現場教育を最優先に。
| 区分 | 内容 | 回収ポイント |
|---|---|---|
| 初期費用 | 審査・マニュアル整備・教育・資材 | 補助金・団体共同取得で圧縮可能 |
| 運用費 | 棚卸・記録・年次審査・ラベル費 | 社内標準化で負荷軽減 |
| 回収方法 | 新規販路開拓・既存顧客維持・見積加点・ESG金融 | 長期的にROI>1を実現 |
“コスト”ではなく、営業投資+金融格付け強化と位置付ける。
公共調達:合法性・持続可能性証明に最も明確な手段。
企業方針:ゼロデフォレ・人権DD要件にCoC文書が流用可。
越境リスク:EU・米・豪など、輸入規制は合法証明を義務化。
→ “最初から認証”のほうが安く早い。
グローバル取引では「認証なし」は取引除外リスク。
ロゴ使用ルール
- サイズ・余白・配置に厳格基準あり。
- 誤表示=信用失墜+契約違反。
B2B資料
認証番号・対象範囲・更新日・証跡フロー図を1枚A4で営業即提示。
B2C発信
「森 → 製品 → 暮らし」のストーリーと地域性で、
“同じ木でも選ばれる理由”を訴求。
「環境配慮」ではなく、「品質と信頼を示す証拠」として伝える。
1️⃣ 認証材の置場を認証/非認証で分割(即日対応)
2️⃣ 出荷伝票に認証ID欄を追加し、写真台帳と連携
3️⃣ 営業用の1ページ説明資料(番号・範囲・更新日)を作成
FSC/PEFCはブランドではなく信用通貨。
「合法性・持続可能性・トレーサビリティ」を
証拠で語れる会社が選ばれる。
森林資源の信頼を“データ化”する仕組みを持つことが、
次世代の競争力になります。
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
安全は“コスト”ではなく 利益の前提条件。
KY/TBM、ヒヤリ・ハット、熱中症・騒音・メンタルケアまでを
チーム運用の型として定着させ、事故ゼロ+強い現場を実現します。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1️⃣ | 今日の作業内容 | 地図・配置図で“見える化” |
| 2️⃣ | 危険ポイント3つ | 具体+対策セットで伝える |
| 3️⃣ | 退避・集合合図 | 緊急連絡網と避難方向を全員で確認 |
| 4️⃣ | 体調確認 | 暑熱・睡眠・薬服用などを共有 |
| 5️⃣ | 役割分担 | 「誰が・何を・いつまで」を明確化 |
朝礼の目的は「今日の安全リズム」を全員でそろえること。
KYカード=“書くこと”が目的ではない。
→ 対策が工程表に反映されたかをチェック欄で確認。
ヒヤリ・ハット報告:
目標:月10件/班(量が質を生む)
形式自由:写真・手書き・音声メモOK
表彰制度:商品券/休暇などでインセンティブ付与
⚙️ 小さな報告を積み上げるチームほど、大事故を未然防止できる。
暑熱対策:
WBGT計で測定、閾値超→休憩頻度UP
塩分タブレット・空冷ベスト支給
寒冷対策:
レイヤリング+防寒手袋+風よけ休憩所
騒音対策:
イヤマフ常用(チーム無線と両立するモデルを選ぶ)
振動対策:
チェンソー/刈払機の連続使用上限を設定
防振手袋+作業交代制
過重サインの兆候
→ 遅刻・集中力低下・ミス増=疲労シグナル
対応:早期に配置転換・作業負荷調整
1on1ミーティング:
週1回10分、リーダーが“聞く”時間
未消化の不満・疲労を可視化する場を設ける
メンタルケアは“特別”ではなく日常の点検項目。
| フェーズ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| T+0〜5分 | 現場停止/二次災害防止/119・上長へ連絡 | |
| T+5〜15分 | 応急処置(気道・出血・搬送準備) | |
| T+15〜60分 | 現場保存・写真記録・関係機関連絡/SNS発信禁止 |
初動60分が再発防止の基礎データを決める。
SNS発信・個人撮影は厳禁。
2in1配置:
(例)重機+チェンソー/左官+防水
→ 欠員に強く、応急対応力が上がる
新入者ロードマップ(30-60-90日)
30日:安全基本(PPE/KY/通報)
60日:技能レベル(工具/設備操作)
90日:品質・原価・改善提案
“多能工化”は安全×効率×雇用安定を同時に高める鍵。
| KPI項目 | 目的 |
|---|---|
| 休業災害件数 | 安全指標の最重要KPI |
| ヒヤリ報告数 | 未然防止活動の量的評価 |
| TBM実施率 | 朝礼・情報共有の質を担保 |
| 教育達成率 | 人材育成と定着率に直結 |
| 欠員補完率 | 組織耐性・業務継続力の指標 |
月次レビュー:
「事故=原因 × 対策 × 再発防止」を1枚図にして全班共有。
失敗の共有速度が安全文化を育てる。
安全MVP:ヒヤリ報告・改善提案・模範行動を評価
改善提案賞:現場発アイデアを表彰
表彰頻度:四半期ごと(年4回)
→ 安全行動が“称賛される文化”を作る
安全文化=“叱る”ではなく“褒めて広げる”。
1️⃣ 朝礼で危険ポイント3つを地図にマーカーで描く
2️⃣ ヒヤリ投函箱を設置(月10件/班目標)
3️⃣ 事故時の60分行動計画をラミネートして重機に常備
安全は“守るためのコスト”ではなく、
「生産性・信頼・人の定着」を高める投資。
チームが同じ地図を見て、同じ行動パターンで動ける現場は、
事故も離職も減り、利益率が上がります。♀️♂️
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
チェンソーは最も身近で、最も事故率の高い機械。
刃の状態=生産性=安全性。
PPEから刃研ぎ・燃料・点検・伐倒・キックバック対策まで、
「事故ゼロと長寿命」を両立する現場基準をつくります。
必須装備
チャップス(または防護ズボン)
⛑️ 安全ヘルメット(遮音シールド付)
✋ 防振手袋
安全靴
ゴーグル
姿勢の基本
腰を落とし、二点支持+体幹安定
片手操作禁止!
退避方向・障害物を先に整理
原因:ガイドバー先端上部(危険域)が木材に噛む。
対策:
上方からの切り込み禁止
くさび併用で逃げ代を確保
チェンブレーキ常用
前足に重心を乗せすぎない
⚠️ キックバックは一瞬で顔面・上半身を襲う。
「刃を木に当てない角度」を体に覚えさせることが最大の防御。
作業域整理(枝払・足元整備)
狙い方向決定(風・傾き・樹冠・障害物)
退避路2本確保(45°後方)
受け口:角度45°、深さ=樹径の1/4〜1/5
追い口:ヒンジ幅1/10〜1/8、水平方向に
→ くさび併用で押し出す
「倒す前の確認に5分、倒すのは30秒」──これがプロ。
目立て角度:25°前後(チェン仕様に従う)
デプスゲージ:0.6〜0.8mm基準
深すぎ → キックバック・振動増
浅すぎ → 切れ味低下
手順:
1️⃣ 左右均等に同回数研ぐ
2️⃣ デプス調整
3️⃣ バリ落とし
4️⃣ チェン向き・テンション確認
研ぎは“力”より“角度”。研ぐ時間で会社のリスクが変わる。
燃料:2スト混合 50:1 目安
→ 長期保管で分離・劣化に注意
チェンオイル:燃料補給と同時に必ず補充
→ 枯渇=焼き付き即故障
冷却清掃:シュラウド・フィン・エアフィルタを毎日清掃
| 頻度 | 主な点検項目 |
|---|---|
| 日次 | チェンテンション/バー片減り/スプロケット摩耗/ブレーキ動作/ナット緩み |
| 週次 | バー裏返し/クラッチ清掃/スターター紐チェック |
| 月次 | 点火プラグ/燃料フィルタ/マフラーのカーボン除去 |
点検結果は「自分の名で残す」──責任が安全を生む。
張力側 → 圧縮側へ切る
順序を誤るとはさまれ・バー噛み込み事故の原因
曲がり・反り・根返りのクセを読む
応力を読める作業者=“刃を止めない人”。
| 事故 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| キックバック | 受け口浅い/追い口で先端刺さる | 受け口角度45°・深さ基準厳守+くさび準備 |
| はさまれ | 張力側を後回し | 応力読み+補助切り・くさび |
⚠️ 事故の9割は「作業手順省略」と「刃研ぎ不足」。
3段階教材構成
5分動画 × 10本(基本〜応用)
現場ドリル × 5
目立て実習(講師・先輩チェック)
対象別:新入/中堅/リーダーで内容を変える
1️⃣ 受け口・追い口寸法をヘルメット内側に貼る
2️⃣ 目立て工具を個人一式化し、管理責任を明確化
3️⃣ 退避路をテープやスプレーで可視化してから切る