-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
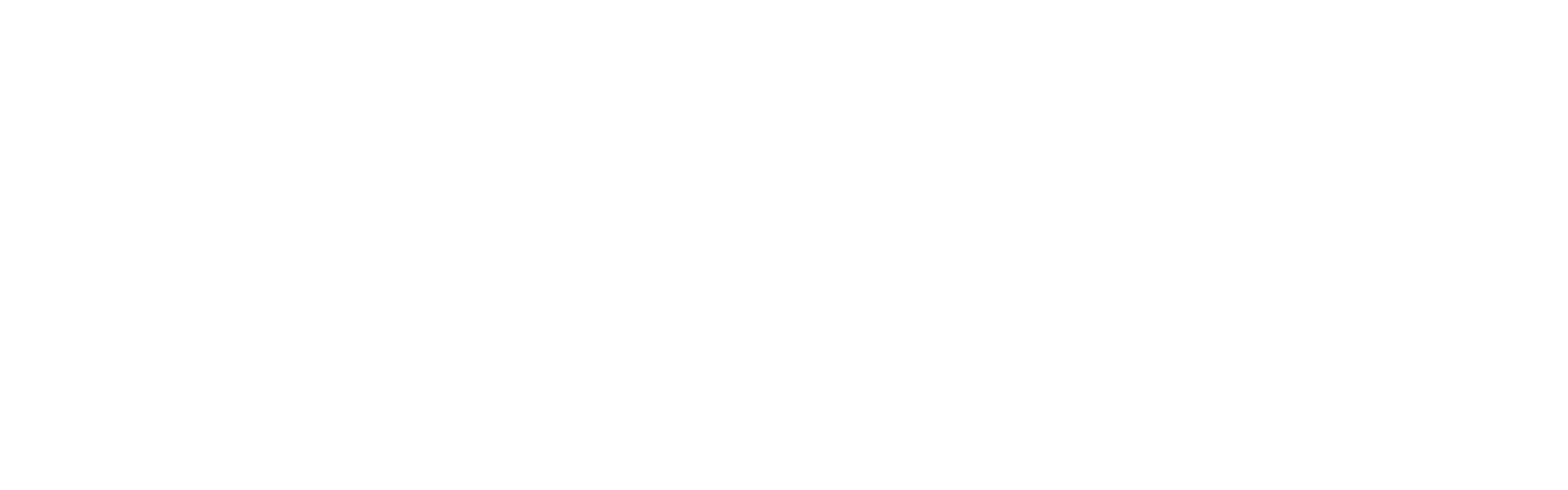
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
~作業道・林道:路網設計のセオリー 🛣️📐~
路網は“通すこと”が目的ではなく、“壊れないこと”と“安く運べること”が目的です。
初期費用が多少高くても、維持補修費と事故・停止損失を含めたライフサイクルコストで最小化を狙います。ここでは計画→設計→施工→維持管理まで、現場で使える指針を一気に整理します🧭。
1) 目的と指標:費用だけでなく距離と安全も 📊
• 路網密度(m/ha):集材距離を短縮し、出来高を底上げする“土台”のKPI。
• 通行等級:作業道(軽車両/小型重機)、林道(大型車両)、幹線林道(10t車)など、使う車両から逆算して断面を決める。
• 安全指標:視距・すれ違い間隔・退避ポケット間隔・法面安定度。見えない安全を図面と標識で“見える化”。
2) 計画:GIS×現地でルート案を作る 🗺️🛰️
• データ:地形図、航空写真、LiDAR、土壌図、地質図、保安林・水域・文化財レイヤー。
• 手順:起点/終点を決め、候補ルートを3案作成→高低差・横断地形・土量バランスで比較→現地踏査で湧水・崩壊地形・巨石の存在を確認。
• 判断基準:縦断勾配とカーブR、切盛土量、カルバート数で維持費の将来値を見積。短いが急勾配の案より、やや長くても安定の案が総合的に安いことが多い。
3) 設計:壊れない断面と排水を最優先 💧
• 縦断勾配:作業道で8〜12%目安、林道で6〜10%目安。長い一定勾配は避け、微妙な折れを入れて速度と排水をコントロール。
• 横断勾配(片勾配):2〜4%。水を片側へ確実に逃がす。
• 路体と路床:軟弱地はクラッシャー敷均し・転圧を丁寧に。路体が負けたら全てが負ける。
• カーブ半径:最小でも12〜15m(車種による)。見通し線を開け、ガードの設置と表示。
• 排水構造:側溝、横断溝(30〜50m毎)、カルバート口の詰まり対策に落葉止め・点検口。
4) 施工:工程と品質管理 🧰
• 土量バランス:切土→盛土の搬送距離を最小化する工程順序。雨期には切土を先行、盛土は乾燥日に集中的に。
• 締固め:ローラの走行回数を記録(写真+回数板)。“転圧したつもり”を無くす。
• 材料:クラッシャー、法面マット、植生土のう。雨前に仮撒きして浸食開始を遅らせる。
5) 維持管理:点検を“制度化”する 🔁
• 定期点検:月1回+大雨後24h以内。側溝・横断溝・法面湧水・路肩沈下をチェック。
• ドローン点検:土場〜幹線の上空写真を定点化し、崩壊の前兆を見つける。
• 台帳:補修履歴・材料・費用・写真を台帳化。次年度予算が作りやすくなる。
6) 環境・法令・合意形成 🏛️🌿
• 保安林・河川・砂防:許認可の想定カレンダーを作り、待ち時間を工程に織り込む。
• 地域合意:境界立会い、騒音・粉じん・通行時間帯の取り決め。住民説明は図と写真で具体的に。
7) 原価と補助:投資判断を言語化 💴
• 初期費用(測量・設計・施工)+維持費(年額)+停止損失(通行止め日数×出来高機会損失)で現在価値を比較。
• 補助制度の採択要件(路網密度・環境配慮・安全)が収益に直結することを社内で共有。
8) 作業道の標準化:写真が現場を守る 📸
• 標準断面図、待避所のサイズ、転回地の直径、ガード設置位置を標準図集に。施工後は完成写真を定点で撮って保全。
9) ケーススタディ:密度30→80m/haで何が変わる? 🧪
• Before:集材距離平均180m、出来高18m³/日、搬出原価7,400円/m³。
• After:集材距離平均75m、出来高26m³/日(+44%)、搬出原価6,100円/m³(▲18%)。通行止めゼロで雨天作業の代替も容易に。
________________________________________
現場で今日からできる3つ ✅
1) 既存路網の排水地図を作り、詰まりやすい横断溝に赤マーク。
2) 大雨後24h以内に簡易点検チェックリストで現場確認。
3) 次の現場に向け、候補ルート3案をGISで作って踏査する。