-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
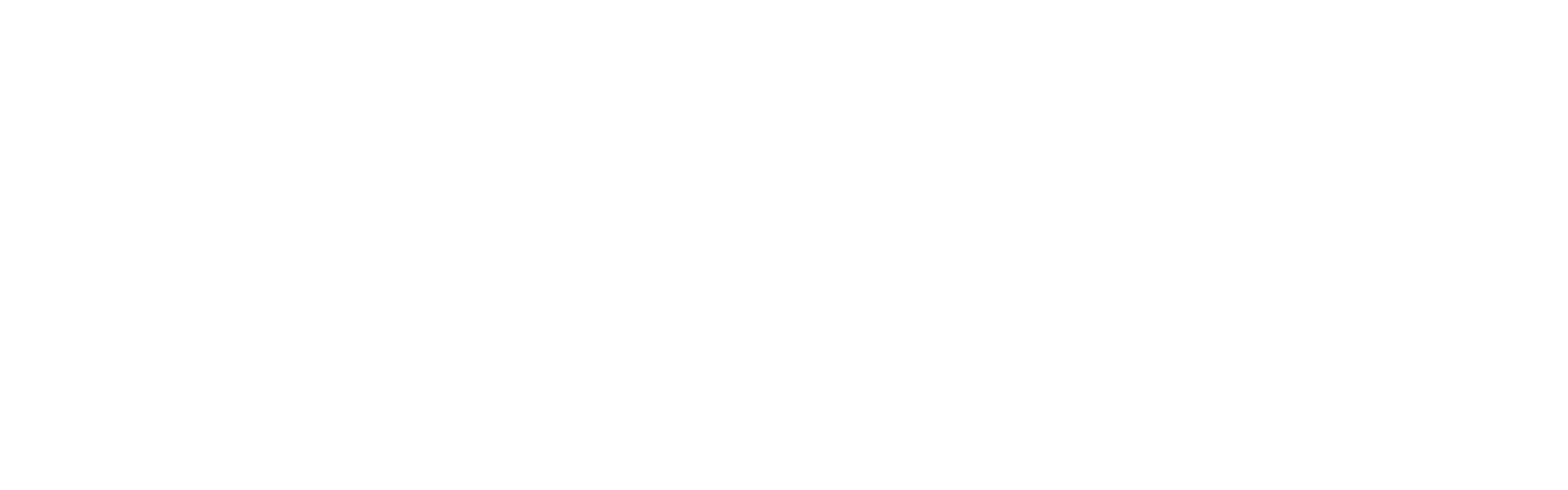
皆さんこんにちは!
株式会社晋林業、更新担当の中西です。
~スギヒノキ人工林の課題とチャンス ~
戦後造成のスギ・ヒノキ人工林は、資源量のピークに向かう一方で、手入れ遅れ・過密・労働力不足・搬出コスト・花粉・風倒リスクなど、多岐の課題を抱えます。しかし“課題がある=価値創造の余地が大きい”ということ。現実的な打ち手を整理します️。
1) 過密→品質停滞→単価低迷の連鎖を断つ ✂️
間伐の遅れは年輪幅・枝下高・曲がり・節に直結し、JAS等級の壁になります。計測のデジタル化(胸高直径分布の自動化、ドローン写真測量、LiDAR)で“証拠を持って”最適密度へ。歩留まり表を現場で更新し続けましょう️。
2) 路網×機械化で搬出コストを削減 ️
路網密度が低いと集材距離が伸び、コストと事故リスクが増大。路面排水・カーブ半径・待避所などの標準仕様を持ち、フォワーダやスイングヤーダと整合する線形で設計。現場の“車線幅”と“旋回”を最初に決めるのがコツです。
3) 花粉・風倒・乾燥化への適応 ️️
品種と更新様式の見直し、混交化、列状間伐、林縁の防風帯整備でリスクを分散。乾燥ストレス増大には下層植生の維持と土壌有機物の回復が効きます。被害前提の“レジリエンス設計”で、保険・備蓄・バックアップ路網も整えます️。
4) 用途開拓:構造材+内装・家具・景観へ ️
節や色を“欠点”ではなく“意匠”に変えるのが2020年代の潮流。内装パネル・什器・小規模建築・DIY材・外構・土木仮設など、径級や等級の幅広さを武器に。乾燥・仕上げ・表面加工で単価を引き上げます✨。
5) カーボン×地域通貨:価値の二重取り
伐採→利用→再造林の循環が回っていることは、クレジットや補助金、公共調達の加点で“現金化”できます。自治体・企業と連携し、地場で“木を使う”プロジェクトを継続的に生み出しましょう️。
まとめ
人工林は“改善の余白”が大きい資産です。データで密度と品質、路網で搬出、用途で単価、カーボンで外部資金。課題を“事業機会”に反転させる視点が鍵となります。